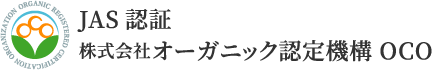梅雨のことが気になり出している。
何しろ日々の生活にも、そして気分にも影響しかねないので、今年の梅雨はどんな感じだろうかと気になるのだ。
大雨や長雨による災害などが起きないことを願っている。
梅雨だの雨だのと聞くと何となくマイナスのイメージを持ってしまいがちだが、心弾むような雨、爽やかな雨、ロマンチックな雨もある。
例えばスクリーンの中に登場する雨。
まず思い浮かぶのは、ミュージカル映画『雨に唄えば』の名場面だ。
ジーン・ケリー扮するドンがどしゃ降りの雨の中で恋の喜びを歌いながらタップダンスを踊る。なんと楽しい雨のシーンだろう。
『シェルブールの雨傘』という映画もあった。若き日のカトリーヌ・ドヌーブがため息が出るほど美しい。哀愁を帯びたテーマ音楽が流れ、ポツリポツリ、そして次第に本降りになっていく雨の中、濡れた石畳の上を色とりどりの傘が行き交う冒頭のシーンがとても印象的だ。
公開から30年たった今でも多くの人が映画史に残る傑作と称える『ショーシャンクの空に』は、無実の罪で囚人となった主人公が自由を手にした瞬間、全身に激しい雨を浴びながら天を仰ぐシーンが感動的だ。
激しい雨といえば、『マディソン郡の橋』の大人の別れのシーンも胸に迫るものがある。ずぶ濡れになった男の薄くなった頭髪からしたたる雨粒が、情熱と抑制とがないまぜになった心情と大人のにおいを絶妙に醸し出していた。
日本映画では、巨匠・黒澤明が撮った圧巻の雨のシーンを抜きには語れない。
何事にもこだわりの強かった“世界のクロサワ”は雨の質感にもこだわった。
『羅生門』では、白黒画面のコントラストをより際立たせるために墨汁を混ぜた雨を降らせ、『七人の侍』では、地面に突き刺さるような激しい雨を撮るために水より重い砂糖湯を降らせたという。
そして、もう一人の巨匠・小津安二郎が唯一撮ったどしゃ降りの雨が、旅回り一座を描いた『浮草』のワンシーン。豪雨の中、道を挟んで男女が激しい罵り合いを繰り広げる。その生々しい男女の感情の高ぶりと激しく降る雨とのコントラストが際立っていた。
とまあ、映画の中のシーンであれば、雨はどれだけ降ろうが、場合によっては降れば降るほど、視覚的にもストーリー的にも効果絶大だ。
しかし、現実の雨となると話は違ってくる。
雨ばかり降っては困る商売もある。
反対に、雨が降らなければ困る商売もある。
雨が続くと助かる人もいるし、困る人もいる。
有機に限らず、作物を育てる農家にとって雨はとても重要な問題だ。
日照り続きの畑にとっては“恵みの雨”も、続き過ぎると作物が病気になってしまうなど悪影響を及ぼす。
集中豪雨ともなれば、一瞬にして畑が駄目になることもある。
近年は線状降水帯という言葉が飛び交うようになった。
積乱雲が列をなすように次々に発生して通過したり停滞したりするため、凄まじい雨が同じ場所で降り続く。
まさにバケツをひっくり返したような雨だ。
そして、この集中豪雨は途方もなく甚大な爪痕を残して去っていく。
自然の猛威の前には人間は非力だ。
命を守る行動につながるように、予測技術の精度向上や情報の早期提供などさまざまな取り組みがされているが、できることはまだまだ限られている。
地球温暖化、気候変動、異常気象、こうした言葉はもはや私たちの暮らしに直結している。
農耕開始の時期を教えてくれる「種まき桜」を頼りにしていた時代とは、季節のリズムも環境も変わってしまった。
自然をコントロールすることはできない。
人間にできるのは考え得る備えをしておくことと、起きた時に冷静に対処すること。
そして何よりもまず、自然の前には人間は非力なのだということを知っておくことではないだろうか。
現実は残念ながら映画のようにドラマチックにはいかない。