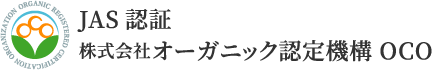新米の季節になった。
何かと物議を醸している米である。
生産者にとっても消費者にとっても生活がかかっている大問題であると同時に、国の未来を揺るがす大問題である。
この度の令和の米騒動で、政府は米の需給予測が間違っていたことを認めた。
そして、今後は主食用米の増産にかじを切ると宣言したが、一度荒れてしまった田んぼはそう簡単に元に戻すことはできない。
その上、担い手不足も深刻である。地球の環境が変わってしまったことも、もはや認めないわけにはいかない。
米づくりは雑草との闘い、重労働との闘い、人手不足との闘い、気候変動や虫の害との闘い、思えば闘うことだらけだ。
後継者がいなければ耕作放棄地となる。
主食である米の向かう道はどこか。
それでも、何とか未来を拓くのが人間の知恵というもので、さまざまな研究、そして挑戦が続けられている。
これから先も持続する米づくりのために何ができるか。
選択肢の一つに「直播栽培」というのがある。
種もみを水田に直接まくというやり方だ。少ない人数で広い面積に行きわたらせることができる。
これまでの米づくりは、ハウスなどで苗づくりをし、それを田んぼに植えて育てる方式である。
国が中心となって栽培指導をしてきた歴史の中でノウハウが確立し、生産者はそのための設備を持ち、それが米づくりの常識となってきた。
安定した品質と収量が確保できたし、ある程度の予測もできてきた。
だが、今ではあらゆる意味でそれが時代にそぐわなくなってしまった。
直播栽培は苗づくりをしなくてよい。田植え作業もしなくてよい。
ドローンや直播機を使えば効率よく広い範囲に播種できて、省力化・低コスト化できる。
苗箱や燃料、ビニールなどといった資源面においての環境負荷も低減できる。
だが、良いことばかりではない。苗が小さいうちは雑草に負けやすい。
その後の生育や収量も天候に左右されやすく、不安定であることは否めない。鳥獣によるリスクもある。
これらを克復しなければならない。
そんな悩みを解決するのが、ロボット技術やICTを活用した「スマート農業」といわれるものだ。
播種や病害虫・雑草の防除といった作業の自動化ばかりでなく、病害虫の発生を把握したり、成育状況の観察や収穫時期を予測できたりと、さまざまなことができるのだ。
なかなか拡大しなかった有機米栽培を後押しする大きな原動力にもなっている。
ドローン、AI、GPSガイダンス、ロボット技術、ICT、IoT等々、現代社会で飛び交う言葉が米づくりの現場を変えようとしている。
「ここが解決できれば」「こんなことができたら」――持続可能な米づくりを模索する挑戦は日々続いている。
もっとも、それをどんなふうに使いこなすのかは人間にかかっているわけだが。