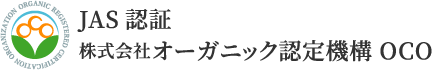「雑草」という名前の草はない。
それなのに、「雑草」と大ざっぱにくくられ、農業の世界では厄介者扱いの憎まれ役だ。
「雑草のように踏まれても踏まれても強く生きろ」と前向きな比喩として使われるにもかかわらず、普段はただ踏まれているか、刈られたり、抜かれたり。
雑草たちにすれば、ごく自然な生命活動の営みでそこにいるわけで、気の毒な話だ。
辞書には、雑草とは「自然に生えるいろいろな草、名も知らない雑多な草」、「農耕地や庭などで栽培目的の植物以外の草」、そして「生命力・生活力が強いことのたとえ」とある。
どれも人間の立場から見た理屈である。
「雑草」と一口に言っても、いろいろなグループがある。
水田や畑、草地など発生する場所による分類、一年草、多年草、さらにイネ科雑草や広葉雑草など、雑草の世界も複雑なのである。
例えばマメ科の雑草にカラスノエンドウというのがある。マメ科ソラマメ属の一年生雑草だ。
同じマメ科でも例えばエンドウマメやソラマメは、「ああ今年もそんな時期だな」と歓迎される。
ところが、カラスノエンドウのほうは「雑草」と呼ばれるのである。
かつて、カラスノエンドウが庭にピンク色の可憐な花を咲かせたことがある。
一面お花畑のようになってうれしくなり、放っておいた。
ところが、である。
気が付くとしっかり根を張り、背も高くなり、他の何ものも寄せ付けないほどの縄張りをつくってしまっていた。
そしてある時、「これは厄介な雑草だよ」と教えられた。
「雑草」と聞いて、にわかに見る目が変わった。
除去に挑んだが、これがとんでもない重労働であった。
「雑草のようにたくましく」という比喩の意味を身をもって実感したのである。
昔は春になると一面のレンゲ畑が見られたものだ。
レンゲソウもマメ科の植物である。
マメ科の植物は「根粒菌」と呼ばれる菌と共生していて、根っこの根粒に空気中から窒素を取り込んでためている。
花が終わったらそのまま土にすき込むと、肥沃な土にしてくれるのだ。
「緑肥」という。まさに窒素を蓄えた肥料である。
それを知っている人間が、稲刈が終わった田んぼに種をまいて栽培していたのが、あのレンゲ畑なのである。
今は田植えの時期が早くなったことや化学肥料が普及したこと、レンゲを食べる外来種の害虫が出現したことなどから、レンゲ畑は全国的にあまり見られなくなってしまった。
カラスノエンドウもレンゲソウも、根にはしっかりと丸いマメ状のものがいっぱい付いている。
ああ、確かにあなたはマメ科だ。
なんだかけなげに思えてくる。
肥沃な土にしてくれるだけではない。アブラムシが付き、それに誘われてテントウムシがやってきてと、虫たちの生態系を豊かにしてくれる。地表を覆って保温・保湿もしてくれていたとは。
こうした「雑草」の力を借りながら作物をつくっている人々の話を聞くと、「共生」ということをつくづく思うのである。
取り決めを交わしたわけでもないのに、互いに助け合っている。
敵に見えても、裏を返せば味方なのだ。
そうやって自然界のバランスは保たれ、成り立っている。
農学博士(雑草生態学)の稲垣栄洋氏によれば、「雑草は自分の得意な所に生えてくる」という。「道路の踏まれるところには踏まれるのに強い雑草、草刈りされる土手には草刈りに強い雑草、草むしりをする庭には草むしりに強い雑草が生えてくる」のだと。
かなわないなと思う。
ところでカラスノエンドウだが、若サヤも花もつぼみも食べられるとは、恥ずかしながら知らなかった。
湯がいてよし、炒めてよし、刻んで乾燥させればお茶にもなるという。
すごい……。
「雑草」なんて呼んでごめんなさい。