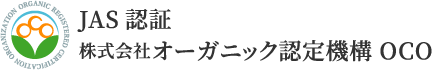日本には古くから続いてきた伝統技術がたくさんある。
藍染もその一つだ。
といって、藍染自体は日本固有のものではない。
藍は「人類最古の染料」といわれるほど歴史が古く、古代から世界各地で染料として使われてきた。
日本では、奈良時代には既に中国からタデ藍の栽培方法、そして藍を甕に入れて発酵させる「すくも法」と呼ばれる染色の技法が伝わっていた。
藍染が最盛期であった江戸時代には、身の回りのあらゆるものが藍で染められ、藍は人々の暮らしと共にあった。
明治の初めに来日したイギリスの化学者ロバート・アトキンソンは、藍染めの美しい青に感激し、「ジャパン・ブルー」と名付けて称えた。
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)もまた、最初に日本の土を踏んだ時に見た店先に揺れる暖簾や人々が身に着けているもの、はためくのぼりなど、目に映る全てが青の風景に新鮮な驚きを覚え、その印象を著書に綴っている。
あふれるほどの藍染の景色がそこにはあったのだ。
だが、明治後期になると合成染料や安価なインド藍などに置き換わり、伝統的な藍染めはどんどん衰退してしまう。
古来からの「天然藍灰汁発酵建て」の技法から生まれる色は、合成された藍や化学薬品を使って染められた色とは異なる。
なぜなら、藍が生きているからだ。
藍の色素は水に溶けないため、発酵の力で溶かして染め液にする必要がある。
「藍還元菌」という微生物が偉大なる功労者(菌)である。
藍液に糸や生地を浸す。そして引き揚げる。
引き揚げてすぐの時は黄土色だ。それを絞って空気にさらすと、酸化して発色する。
ベテランの染め師でもその度に感動するほど、とても神秘的で美しい瞬間なのだという。
藍の液に浸してはさらし、浸してはさらしと、これを何回も、何十回も繰り返すことで青に深みが生まれる。
藍の色は「藍四十八色」といわれ、その全てに名前が付いている。
1回染めの最も淡い色は、ちょっと甕を覗いただけという意味から「甕覗き」という。
何十回も染めを重ねた黒に見えるほど濃い色は「褐色(かちいろ)」。戦国時代には「勝色」と字を当てて、武士が武具などをこの色に染めて縁起を担いだ。
今は、多くは化学薬品を使う「化学建て」という方法だ。石油からつくられる合成藍もある。当然、かかる労力もコストも、そして価格も大きく異なる。
だが、昔ながらの藍染めは、川を汚すことなく、生きものたちと共生できる。畑にまけば肥料にもなる。
自然や人の体に害を及ぼさない、地球に優しい持続可能な染色方法である意義が再び見直され、藍染を愛する人たちによって伝統産業として新たな模索が既に始まっている。
自然から写し取った色は年月ともに変化し、その度に味わいを変えていく。
自然と共にある豊かさとはこうしたことかと気が付けば、世の中はもっと変わるのかもしれない。
自分のシミやシワも、味わいが増したのだと思って愛おしむことにしよう。