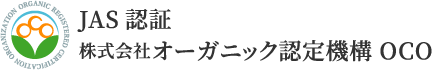ペットボトルは食品トレイや繊維製品などにリサイクルされる。
古紙は新聞紙や雑誌、トイレットペーパーやティッシュペーパー、段ボールなどにリサイクルされる。
というわけで、ごみの日には分別して出すのが当たり前になっている。
環境に負荷をかけないためにはどうすればよいかと人は考えるようになった。
持続可能な社会のために何ができるか、日々いろいろ模索し、頑張っている人がいっぱいいるのだ。
例えば、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学で、プラスチックに代わる容器として「竹」の容器が研究開発されている。
プラスチックの容器は、耐熱性や安定性を維持するために“永遠の化学物質”と呼ばれる有機フッ素化合物PFASが使われている。
自然の環境下で分解されにくく、長期間残り続けるものだ。
プラスチックのうち、実際にリサイクルされるのはほんの一部である。
リサイクルには、プラスチックをプラスチックのものへ再生する「マテリアルリサイクル」と、化学分解した後にプラスチック製品に再生する「ケミカルリサイクル」、そして熱源として利用する「サーマルリサイクル」がある。
サーマルリサイクルは、燃やして熱エネルギーを回収するというもの。
日本ではリサイクルの中で実はこれが一番多いのだが、大量の二酸化炭素を排出するという問題がある。
ちなみに、欧州ではこれは「熱回収」や「エネルギー回収」と呼ばれ、リサイクルとはみなしていない。
いずれにしても、プラスチックは気候変動、生物多様性の喪失、汚染など全てに影響する。
「竹製の容器」は、そのプラスチックを使わずに済む代用品として期待されるのだ。
竹は成長が早いので安定的に供給できるし、生分解するスピードも速く、環境を汚染しない。
耐熱性や安定性を保つ秘密は「でん粉」だという。
この竹のプレートが食品トレイやテイクアウトの容器に使われるようになったら、脱プラスチックへの新しい扉が開くことになる。
自然は利用するものではなく、その力を借りるものなのだとあらためて気付かされる。