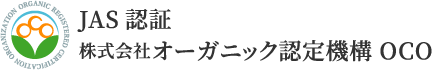オーガニック野菜は農薬不使用ではない――と書くと一瞬戸惑うかもしれないが、まだまだ誤解がある言葉なので、あえて記してみよう。
「オーガニック」とは日本語に訳すと「有機の」という意味である。
化学肥料や合成農薬に頼らずに、水、土、太陽、生物など自然が持つ本来の力を活かした農林水産業や加工方法のことを指す。
“有機の国連”ともいわれる国際NGO「IFOAM(国際有機農業運動連盟)」は、オーガニックが依拠すべき基本法則として「健康」「生態系」「公正」「配慮」の4つを掲げている。
「全ての命を幸せにする仕組み」、それがオーガニックの目指すものである。
有機栽培は農薬を全く使えないというわけではない。
「有機野菜」と「オーガニック野菜」は同義語で、農林水産省による「有機JAS」と呼ばれる規格で求められる条件を満たした野菜を指す。
この認定を受けていなければ、「オーガニック」「有機」などと表示することができない。利用可能な薬剤の基準も定められている。
つまり、「無農薬」や「農薬不使用」ということではないのだ。
一方、「無農薬野菜」とは、全く農薬を使わない野菜のことである。
しかし、圃場の残留農薬や近隣の田畑で使用した農薬が検出されるケースや、無農薬と偽った表示が登場したことで、現在は農林水産省のガイドラインで「無農薬」と表示することは禁じられている。
それに代わる表示が「特別栽培農産物」というものだが、この言い方で農薬を全く使っていないということが消費者に伝わっているのか疑問である。
農薬を一切用いない究極の農法といわれているのが「自然農法」である。
農薬や肥料を使わないのはもちろんのこと、畑を耕すことも、除草もしない。自然の本来持っている力だけを借りるのである。
いずれの方法も生産者にしてみれば、非常に大きな労力を必要とすること、品質や収穫量が安定しないこと、資材などのコストがかかることは共通の悩みである。
手間が掛かればその分、値段も高くならざるを得ない。
消費者は、高ければ買いたくても手が出ない。従って、なかなか浸透しない。
「オーガニック」も「特別栽培」も「自然農法」も、体にいい、環境にもいい、他の生きものにとってもいいと分かっていても、日本においてはそう簡単に「当たり前」にはならないのが現実である。
この負のループを立ち切るすべはないものか。
一つの手段としてスマート農法が動き出している。
ドローンで農薬を散布している様子はもう既によく見掛ける光景となった。
もちろん、ここで言う農薬は規定の範囲内という意味である。
今はAIのセンシング技術を使って、ドローンに搭載したカメラの画像から病害虫の発生を診断したり、成育状況を把握したりできるという。成育度合いが分かれば、生産者はそれに合わせた作業をすればよい。生産効率はぐんと上がるだろう。収穫時期の予測もできる。
技術の進歩というのはすごいものだ。
有機栽培に取り組む生産者はまだまだ少ない。
立ちはだかる壁が一つずつ取り払われ、有機野菜が当たり前に食卓に並ぶ日がそう遠くない未来であることを願う。