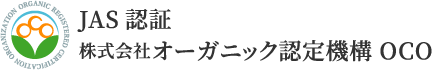夏真っ盛りだ。
熱中症も怖いし、夏バテも怖い。
油断をしていると命取りになるほどの暑さである。
が、それでも何だかふつふつとエネルギーが湧きたつのもまた夏である。
日本全国お祭りの季節。心が躍り、血が騒ぐという方も多いだろう。
お祭りといえば、行き交う浴衣姿もまた風情を盛り上げる。
今、若者や海外から来ている人たちの間で浴衣は人気のファッションアイテムだ。
思い思いの浴衣を着て、素足に下駄だけでなく、サンダルやスニーカーを合わせるなど、自由な発想で楽しんでいるのである。
やはり、夏には浴衣がよく似合う。
だが、浴衣はもともとは夏のものではない。
浴衣の原型は、平安時代に貴族たちが入浴の際に着用していた「湯帷子(ゆかたびら)」という麻の薄い着物である。
入浴といっても、当時は今のように湯に浸かるのではなく、水蒸気を浴びる蒸し風呂だった。
そのため、火傷防止、汗取り、そして複数で入るので裸を隠す目的から湯帷子を着ていたわけで、あくまでも下着であって、人前で着るものではなかったのである。
浴衣が大きく進化したのは、町人文化が花開いた江戸時代のことだ。
それまで輸入品で高価だった木綿が国内で大量生産されるようになり、庶民の着物の素材は麻から木綿へと急速に変わった。
時期を同じくして銭湯が普及し、湯船に浸かる入浴スタイルになった。
そうなると、浴衣は湯上りに体の汗を拭き取るためのものとなり、「身拭い」と呼ばれた。今のバスローブのようなイメージである。
江戸後期には、入浴後に浴衣のまま風呂屋の二階で涼む習慣が浸透し、「湯帷子(ゆかたびら)」は略して「ゆかた」となり、「浴衣」の字が当てられた。
こうして浴衣は、もともとの下着から家庭でくつろぐ時や寝間着として、さらには外出着へと次第に格上げされていったのである。
浴衣は素材といい構造といい、蒸し暑い日本の夏にとても適していた。
当時の浴衣は白地か紺地が主流で、人々は昼は白地、夜は紺地の浴衣を着た。
白地は熱を吸収しにくいので真夏の日中を涼しく過ごせ、見た目にも爽やかだ。
一方、夕方から夜にかけて紺地を着た理由は、染めに使われる「藍」の香りを虫が嫌うからだ。蛇さえ寄せ付けないという。
天然の藍には防虫効果の他にも、解毒や殺菌・抗菌、止血効果があり、薬草としても古くから用いられてきた。
今では科学的に証明されているそうした効能を、昔の人たちはよく知っていたのである。
藍で染めた布は強度があって、燃えにくく、保温にも優れていたことから、火消しのはっぴや農作業時の野良着、蚊帳、手拭い、のれん、赤ちゃんの産着やおしめなど、生活の中のさまざまな場面に使われていた。
天然・自然のものから、人工的・化学物質の時代へと移った結果、地球の環境は変わり、私たち人間はアレルギーなどさまざまな不調に悩まされるようになった。
そして今、自然のもの、天然のものが持つ力が再び注目されている。
現代のわれわれが悩まされていることを解決する糸口が、案外いにしえの人々の暮らしの知恵に見つかるかもしれない。
科学技術の進歩とともに手放したものや切り捨てたものたちの中に、何かヒントがあるかもしれない。
カラフルな浴衣姿に新しい時代を感じながら、そんな思いを巡らせている。