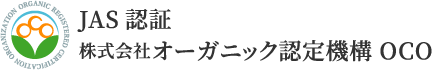年々暑くなる。
猛暑、酷暑で、クールビズもスーパークールビズも追いつかない。
クールビズ…… “夏場の軽装による冷房節約”をキャッチフレーズに、2005年に環境省が環境対策として打ち出してスタートした。
ノーネクタイ、ノージャケットで、過度に冷房に頼らずに快適に過ごそうというものだった。
「涼しい」「格好いい」という意味のCOOLとビジネスの短縮形を掛け合わせた造語で、当時はネクタイをしなくていいというだけで画期的な響きがあった。
しかし、その割には実際にはなんだかあまりカッコイイ感じがしなかったのは、皆、着慣れていなかったし、見慣れてもいなかったからだろう。
訪問先や相手によって、ネクタイをするべきか、外すべきかという新しい悩みも生まれた。
2011年には東日本大震災による電力不足対策で「スーパークールビズ」が提唱された。
これまでよりもさらにカジュアルな服装が許容され、ポロシャツやアロハシャツ、チノパンにスニーカーもオーケーとなり、室温管理の徹底や、時差出勤や在宅勤務など働き方を見直すきっかけにもなった。
そして2021年以降、環境省によるクールビズ実施期間の設定は廃止され、企業や個人がそれぞれの状況に合わせて柔軟に判断することになった。
何しろ年々暑い日が増え、異常な気温を記録するようになり、しかも状況は地域によっても違う。もはや一律に設定できる時代ではなくなった。
20年の月日が流れたのだ。
働き方が多様化し、職場でのカジュアルな服装は普通になった。
「クールビズ」「スーパークールビズ」という言葉がもはや死語ではないかと感じるほど、その考え方は定着し、当たり前になったということだし、事態はもっと深刻になったということだ。
かつて日本の夏といえば、窓や戸を全部開け放して風を通し、すだれやよしずで日差しを遮り、玄関先に打ち水をして気化熱を利用するといった工夫で涼を取り込んでいた。
風鈴のチリンチリンという音は耳に心地よく風を感じさせた。
敷物をい草に替え、麻や綿素材を身に着け、金魚鉢の中で涼しげに泳ぐ金魚を眺めてと、目や耳や肌など五感から清涼感を得るアイデアが暮らしの中にいっぱいあった。
汗を拭き拭きかき氷を食べてキーンと頭の先まで冷やし、うちわであおいで風を送る。
自然を上手に涼感に変え、そして使う動力は自分自身。まさにエコだった。
それで何とかしのげる時代だったのだ。
今は熱中症警戒アラートが出されたら外出を控えるほうがよいとされ、エアコンに頼らなければ命取りになる。
携帯扇風機を片手に町を歩き、屋外や空調のない所で作業をする人たちはファン付き作業着を着てと、涼を取るためのアイテムも変わった。
だが、快適な温度にばかり身を置いていると、今度は体のほうは冷えに慣れて汗をかかなくなり、汗腺が退化して体温調整機能が働かなくなってしまう。
外の気温と部屋の温度の差が大きいと、出たり入ったりする中で自律神経やホルモンバランスを崩してしまう。
暑いのを我慢し過ぎても体に悪い、快適過ぎても体に悪い、何とも悩ましい。
これが、現代の夏なのである。
持続可能な地球環境の実現のためにCO2の排出量を減らそう、再生可能エネルギーを利用しよう、生態系を守ろう、資源を有効に使おう、エアコンの設定温度は28℃を目安にしよう、節電・節水に努め、ゴミを減らそう、そんなさまざまなフレーズが飛び交っている。
一人一人の行動が不可欠なのは分かっている。
一方で、夏はどんどん暑く、長く、そして過酷になっている。大規模災害も増えている。
世界の足並みもそろわぬ中、目の前の現実に対して一体どんな打つ手があるのだろうか。
エアコンの利いた快適な部屋の中でそんなことを考えている自己矛盾に、気持ちの悪い汗がにじむ。
それでも、自らの生きるべき時期がくると、夏野菜は実をつけ、虫たちは活動し、鳥も動物も生命をつないでいく。
人間が一番軟弱な生き物に思えてくる。