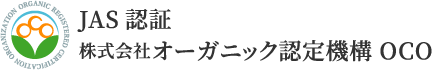「和食」がユネスコの世界無形文化遺産に指定されたのは2013年のこと。
ヘルシー志向とも相まって世界で和食ブームが巻き起こり、日本食レストランも次々にできた。
和食には何といっても日本酒が合う。
日本が誇る発酵の食文化の一つ「日本酒」にも外国人の興味が注がれるようになった。
海外における日本酒の認知度は高まり、ブランド価値が向上し、輸出はコロナ過の時期を除けば順調に伸び続けている。
その一方で、国内では日本酒の消費量は低下の一途をたどっている。
日本酒造組合中央会の調査によると、日本酒の国内出荷量は2023年は1998年の約3分の1だという。
減り続ける国内需要、伸び続ける海外需要。
そんな中、2024年12月、ユネスコの無形文化遺産に日本の「伝統的酒造り」が登録された。
インバウンドの増加で、来日時に日本酒を体験してハマる外国人も多く、日本酒は相変わらず人気なのだ。
和食が身近なものになったことで、合わせるお酒もおのずと注目されるようになったわけだ。
かつて、フランス料理といえば、合わせるお酒はワインだった。
ところが、1970年初頭、素材の味を生かす新しいフランス料理「ヌーヴェルキュイジーヌ」が広まったことで話は変わってくる。
これには日本料理が大きな影響を与えたとされる。
そして、フランスのソムリエたちが日本酒を取り入れ始めた。
日本側も積極的に啓蒙活動を行ってきた。
その結果、現在では世界の名だたるワイン・テイスティング大会の多くが日本酒部門を設置しているという。
海外で好まれる日本酒は軽くてフルーティーな味わいのものだ。
ここに重点を置いて海外市場をつかもうと、酵母を増やし、アルコール成分は減らして、まるでワインのようなテイストの日本酒を生み出した。
そして、冷やしてワイングラスや、さまざまな素材の酒器で味わう楽しみも付加価値としてPRした。
これが大いにウケたのである。
「酒」は「SAKE」となり、ブランド力は一気に向上した。
国も輸出拡大に力を入れている。
支援策の一つとして、令和2年に輸出に限定した「輸出用清酒製造免許」が新設された。
これによって、最低製造数量基準などといった要件のハードルが下がり、高付加価値商品を少量から製造できるようになって、新規参入もしやすくなった。
ただし、あくまでも海外輸出品製造という限定免許であるため、原材料の米・米麹は国内産米のみを使用し、製造・容器詰めも国内で行わなければない。また、この免許で製造した清酒は国内販売は原則禁止されている。
「アルコール離れ」がいわれる中、海外市場は日本酒の向かうべき一つの道であることは間違いない。
EUとの間で「有機酒類」が同等性の対象となったことは朗報である。
ところで、海外で日本酒が好まれるようになった背景にはもう一つ、健康志向がある。
有機農法で栽培された酒米を使用した日本酒は、オーガニック志向の高い外国人に選ばれているのだ。
さらに、「ヴィーガン」人口が多い欧米では、米と麹と水が主原料である日本酒は動物由来の成分が含まれない安心して飲めるお酒ということで注目されており、ヴィーガン認証を取得した銘柄も増えている。
「ヴィーガン認証」に「オーガニック認証」、思えば日本酒を取り巻く風景もずいぶんと様変わりしたものである。