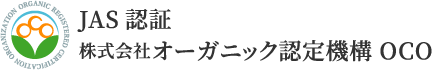新入学の季節だ。
小学校に入学する子どもたちにとっては初めて体験することがいっぱいだ。
「給食」もその一つだろう。
日々変わる献立、友達とみんなで食べる楽しさは格別だし、初めての食材に出会うことだってあるかもしれない。
給食といえば、50歳以上の人であれば懐かしのラインナップは「コッペパン」「鯨の竜田揚げ」「ソフト麺」あたりだろうか。
粉ミルクを水で溶かして温めた「脱脂粉乳」という時代もあった。
鯨は当時捕鯨大国だった日本の貴重なたんぱく源で、鯨の竜田揚げは給食の人気メニューだった。
そんな昭和の給食体験者にとっては、今どきの給食は隔世の感があるだろう。
驚くほど質が高くなっている。
おいしいだけではない。
季節にちなんだ行事食や郷土料理から世界の料理まで、メニューのバリエーションも豊富だ。
日本で最初の学校給食は、明治22年に山形県の鶴岡町(現鶴岡市)の大督寺境内に建てられた私立忠愛小学校で始まった。学校給食
貧しくて就学できない子どものために僧侶たちが宗派を超えて協力して開いた学校で、お弁当を持参できない児童のために無償で昼食を提供した。
托鉢によって得たお米やお金で用意した塩むすびに塩鮭、菜っぱの漬物であった。
善意から始まった給食は各地へと広がり、昭和の時代には国の施策となった。
戦争によって一時途絶えたが、終戦後、学校給食法が制定され、給食は欠食児童対策から教育活動の一環と位置付けられた。
時は流れ、令和時代の給食は、食育、地産地消、安全・安心、そして健康志向と、まさに時代のキーワードが全て反映されたものになっている。
栄養教諭や栄養士の研究の下に作られる献立は、安全管理が徹底され、栄養バランスはもちろん、糖質や塩分、家庭で不足しがちな栄養素など、さまざまな面から子どもの健康に配慮して作られている。
食物アレルギーを持つ子どもや、イスラム教に対応したハラール給食などの特別食の提供もされている。
その陰には、献立作成を担う現場の人たちの並々ならぬ苦労がある。
楽しみにしている子どもたちのワクワクを裏切らないようにと、限られた予算と物価上昇の中、日々奮闘しているのである。
子どもたちは給食を通してたくさんのことを学んでいく。
食べるということの意味、体のこと、調理しくれる人のこと、生産者や地域のこと、環境のこと、世界のこと、地球のこと。そして、感謝するということ。
今、地場で生産された農産物を給食に取り入れる学校が増えている。
また、有機農産物を使ったオーガニック給食を採用するところも出てきた。
次代を担う子どもたちに地域の伝統食を伝えたり、環境に負荷をかけずに自然と共生する農業の大切さを伝えたりと、食育の面でも期待されているのだ。
有機野菜に挑戦したくても販路の開拓が一つの障壁となっていた生産者にとっては、給食は量が多いし計画も立つので、将来への道筋が開ける。
移住者も含め、若い新しい担い手が登場しているところもある。
彼らは、野菜の種類の確保や安定供給が難しいなど小規模農家のデメリットとされる面を、新しい時代のツールを使って仲間とつながり、共同し、柔軟に克服していく。
学校給食の始まりは欠食児童の救済あった。
孤食、偏食、欠食など、子どもの食を取り巻く問題の質は変わったものの、現代においても、学校給食の担う役割は大きい。
子どもたちの「おいしい」の声が聞こえ、はじけるような笑顔が見える。
それが生産者たちのやりがいにつながり、持続可能な農業へとつながり、農家の担い手不足問題を抱える地域に光を灯すことにつながるかもしれない。
そんなふうして皆がよいように回っていけばいいなあと、そんなことを思いながらピカピカの一年生の姿に目を細めている。