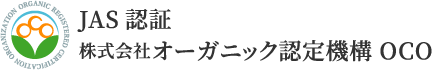「The World of Organic Agriculture2024」が発表された。
FiBL & IFOAMが発表している統計年鑑の2022年のデータを対象にしたものだ。
世界の流れを見ると、有機農業は目覚ましい拡大傾向を見せている。
日本はというと、残念ながらまだまだ。
そう、まだまだなのである。
世界の有機農地面積は2022年には前年比26.6%増という勢いで、多くの国で有機農地の大幅な拡大が報告されている。
日本はといえば、0.37万ha増えて前年比0.1%増。
伸び悩みの感が否めない日本だが、それでもオーガニック食品市場は成長しており、2017年に比べると21.1%の大幅な増加を示している。
消費者の32.6%が少なくとも週に1回はオーガニック食品を購入しているというから、17.5%だった2017年の調査から大きく前進だ。
だが、それでもやはり日本はオーガニック後進国であるという現実。
なぜ日本のオーガニック意識は低いのか。
その前に、なぜヨーロッパはオーガニック意識が高いのか、である。
これを考えていくと、なるほどな……と、簡単には越えられない壁の厚さというか、高さを実感する。
そもそも、オーガニックの始まりは「オーガニックムーブメント」といわれる社会運動である。
今から100年前、化学肥料や合成農薬に依存する近代農業の体制に異議を唱えて立ち上がった欧州中の生産者を中心とする市民が、当時ドイツ領だった場所で集会を開いたのが原点だ。
つまり、オーガニックを支えているのは市民の意識と力なのだ。ここが日本とはそもそも大きく違う。
オーガニック発祥の国といわれるドイツでもオーガニック食品は割高である。
それでも人々は積極的に買う。なぜか。
それは「自分を越えた先にある」という考え方だ。
日本の場合、オーガニックを買う主な理由は、自分の家族の健康のため、おいしいから、安心安全だから。つまりパーソナルベネフィット――個人の利益だ。
それに対してドイツでは、地元農家支援のため、動物愛護のため、環境や人体に害が少ないから、食のスキャンダルが少ないから。つまり、ソーシャルベネフィット――社会的利益としてのオーガニックを認め、オーガニックであることに対して費用が支払われているのだという。
オーガニックは高いけれど、搾取されたりアンフェアな状態に置かれたりしている人の人生を救える、その社会的な利益のための対価としては決して高くはないのだと。
世界一のオーガニック社会であるという自負が感じられるではないか。
良いものを大事に長く使う、限りある資源を尊ぶというドイツ人の美学。
そして、誰かがやってくれるのではなく、一人一人が社会問題に能動的に関わることで自分や大切な家族を守るという考え方。
当然、生産者、製造者、研究者などへの手厚い公的財政支援があり、安心してオーガニック農業に従事できるし、研究が可能なのだ。
そんな中から世界中で知られるオーガニックメーカーが生まれてきた。
ドイツには全国にチェーン展開する大手のオーガニックスーパーだけでも700軒以上の店舗がある。最大手のスーパーでは、1店舗で約6万種類ものオーガニック商品を提供しているというから驚く。
日本にはオーガニック商品だけを集めたスーパーはほとんど存在しない。
だが、変わってきているのも確かだ。
日本大手スーパーマーケットチェーンがオーガニックに力を入れる意志を表明している。2023年4月には産官学が連携し、利害や資本を越えてオーがニックの志で集まった事業体による有機加工食品コンソーシアムが立ち上がった。
もちろん日本にも慣行農業が定着する前から自然農法をやっていた人はいたし、戦後から有機農業に取り組み、消費者に提供してきた実績のある人々もいる。
新鮮な無農薬・低農薬野菜を個人的なルートで提供している農家もいるし、宅配サービスをしている企業も数々登場している。
始まりはビジネスでも、オーガニックは確実に暮らしの中に浸透してきている。
暮らしを営む一人一人が何を選ぶのか。
日本のオーガニック社会を支えるのも、地球の今、そして未来を左右するのも、われわれ生活者自身なのである。
参考
IOB Journal(なぜ、オーガニック先進国ドイツでオーガニックがここまで広まったのか。パーソナルベネフィットを超えるソーシャルベネフィットとしてのオーガニックとは。2020.9.10更新)
一般社団法人日本伝統野菜推進協会(急拡大した世界のオーガニック市場-「The World of Organic Agriculture2024」を読む 2024.11.6更新)
農林水産省(「有機農業をめぐる事情」令和6年9月)