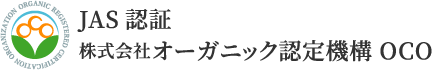いきなり私事で恐縮だが、津軽の友人からリンゴが届いた。
昨年は猛暑などの影響で不作に泣いたリンゴ農家だけに、「今年は、数は少ないが出来は良い」という言葉にはずっしりと重みがあった。
箱を開ける前から、あたりに芳香がこぼれている。
ここに届くまでにどれほどの手間と愛情がかけられているかと想像すると、愛おしさもひとしおだ。
リンゴの花は同じ品種同士では授粉せず、実がならない。
「自家不和合性」といって、遺伝的多様性を維持するためのメカニズムである。
受粉し、結実させるためには、遺伝子型の異なる複数の栽培品種を混植するか、授粉専用品種を導入して人為的に授粉させる必要がある。
授粉の方法は、人の手で花粉を付けていく人工授粉と、花粉媒介昆虫の助けを借りるという2つだ。
かつて、リンゴ農家は一つ一つ手作業で授粉を行っていた。
リンゴの花が咲いてから散るまでのわずか10日ほどの間にこの骨の折れる作業を集中してやるわけで、当然のことながら人出不足の問題に突き当たる。
そんな津軽のリンゴ農家の救世主となったのが、「マメコバチ」という体長1センチほどの小さなハチだ。
体は小さいが、たいそうな働き者で、今では全国的にリンゴ栽培には欠かせない存在になっている。
50~60メートルほどの範囲で花から花へと飛び回り、花粉を集めて巣に運ぶ。2~4キロも遠出するミツバチに比べると移動できる距離は随分短いが、授粉能力は何十倍も上回という。
リンゴづくりのパートナーとしてマメコバチに白羽の矢が立ったのは、もともと津軽の人々の身近いたからだ。
マメコバチは河川敷やかやぶき屋根の葦の筒に巣を作る。巣を割ると中には花粉の塊が並んでいて、子どもたちのおやつになった。
その団子状になった花粉の色と形が大豆を炒って挽いたきな粉、つまり「豆粉」に似ていることから、「豆粉蜂」という名前が付いたという。
マメコバチは集めた花粉を固めて団子状にし、その中に卵を産み付ける。
一度産卵すると土で壁を作り、その手前にまた花粉団子を作って産卵してと、1本の葦の中に8つぐらいの部屋を作る。
卵が孵化すると幼虫は花粉団子を食べて育ち、やがてまゆを作る。そして成虫となってその中で越冬し、春先に飛び立つ。
リンゴ農家は、重労働を代わりにやってくれるこの大切なパートナーを、来るべき時のために大切に保管している。葦から外したまゆを、リンゴの授粉に適した時期がくるまで冷蔵庫に入れてコントロールするのだ。
津軽地方でマメコバチの飼育が始まったのは1940年代のこと。
リンゴの授粉に活用しようと思い付いた人物が、葦の筒を使って飼育を始めた。
在来の生きものの力を借りるという画期的な発想は、その後、青森県の研究機関と農家の工夫や努力の積み重ねによって、マメコバチの飼育・管理技術として確立した。
古くから身近にいた生きものが思いがけない頼もしい助っ人となり、農家の暮らしを支え、地域の産業を支える「縁の下の力持ち」となったのである。
そして、この青森発のリンゴ栽培技術は全国へと広がり、世界も注目するものとなった。
さて、マメコバチの力を借りるということは、彼らの活動状況に大きく左右されることになる。
まず、個体数を維持し元気に働いてもらうためには、巣づくりができる“優良物件“を用意することが重要だ。すみかとなる葦の確保は、マメコバチにとってもリンゴ生産者にとっても死活問題である。
冬の間の巣の適切な管理も重要だ。前年の天候も大きく影響する。とりわけ温暖化は、マメコバチの管理においても非常に深刻な問題となっている。
持続可能なリンゴづくりのために、農家とマメコバチの奮闘は続く。
リンゴの産地である青森県板柳町では、毎年5月に「マメコバチ感謝祭」が開かれるという。パートナーに感謝と敬意を――なんとも心温まる話である。