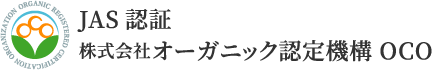今、地球環境は産地の地図も塗り替わるほどに変化している。
従来どおりのやり方では、稲作も野菜づくりも立ち行かない。
持続可能な農業のためには何をすればよいのか。
例えば、土壌を健康に保ち、環境も生きものも健康に生きられるような農業をと、オーガニック(有機)の米づくりに取り組んでいる人たちがいる。
例えば、耕作放棄地を再生・活用するためのさまざまな取り組みをしている人たちがいる。
例えば、「田んぼ」がなくても米が作れるとしたら……夢のような話である。
ところが、夢ではないのだ。
「宇宙ステーションでも米を育てたい」という想いから生まれた新しい品種がある。
「みずのゆめ稲」という草丈15~20cmの短い稲で、わずか2カ月で収穫が可能になる超早生稲である。
さらに驚くことに、施設の中で温度や湿度、光の管理、液肥やCO2なども自動制御され、野菜の水耕栽培のように多段式で栽培でき、なんと最大6回の収穫が可能になるという。
コンテナのような小さな空間でも栽培が可能だ。
もちろん農薬は一切使わない。
長年にわたって研究を重ねてたどり着いた、「田んぼ不要の新たな主食生産モデル」だという。
田んぼがなくても米が育つとなれば、どんな土地でも、過酷な気象条件下でも、例えば災害に見舞われたとしても、米づくりが可能になる。
つまり「宇宙ステーションでも米が作れる」というわけだ。
高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加といったたくさんの難題を解決する手立てになるかもしれないし、完全無農薬で環境負荷も低減できるとあれば、世界中の未来の農業を大きく変えるかもしれない。
「農」という字は2つの漢字から成り立っている。
上半分は大地を覆う「木」の象形が2つ、下半分の「辰」は2枚貝がカラから足を出している象形だという。
つまり「農」という字は、貝殻で作った道具を用いて林野を切り開くことを表している。
農業を意味する英語「agriculture」は、ラテン語の「ager」(土地)と「cultura」(耕作)という2つの言葉から成り立っている。
さて、耕さなくてもよいとなると、果たしてそれは「農業」と呼ぶのだろうか?
何かふさわしい新しい言葉が生まれるのかもしれない。
そういえば、太宰治の小説『正義と微笑』の中に、教師が辞めていく際に「ゆったりと、真にカルチベートされた人間になれ!」と生徒に熱く語るくだりがある。
カルチベート「Cultivate」には「耕す」という意味のほかに、「人間としての内面の能力を磨き育む」といった意味がある。これも語源は「耕作」を意味するラテン語だ。
世の中はどんどん変わっていく。
変わるべきこと、変わってはいけないこと、ちゃんと地に足をつけて立っていないと見失ってしまいそうだ。
どうやら、耕す必要があるのは人間の側のようである。
参考
知財図鑑 知財ニュース 田んぼ不要、無農薬で年6回収穫できる「みずのゆめ稲」を開発(2025.07.08)