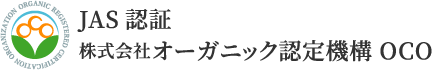明治の初め、日本を訪れたイギリス人が、町じゅうにあふれている藍染の青を見て「ジャパン・ブルー」と名付けた。
染物屋が「紺屋」と呼ばれたほどに、藍染の青はまさに日本の色だったのである。
そんな日本でさえ、その後は化学染料的な手法へと移っていった。
現代の藍染の多くが植物由来の染料を使ったものではなくなっている。
天然の藍を使い、微生物の発酵の力によって染め上げる「天然藍灰汁発酵建て」という古典的なやり方を行う工房は、今は数えるほどである。
それでも、現在も存続し続けている日本は、世界的に見ても奇跡的なのだという。
タデ藍の葉を細かく刻んで乾燥させた後、長期間発酵・熟成させてつくる「すくも」が染料のもとである。藍染の良しあしを決める肝だ。
藍を寝かせ、水を打ち、切り返し、これを繰り返してムラなく発酵させる。
こうしてできた「すくも」は土のようにほろほろとしている。
この「すくも」を甕の中に入れ、天然灰汁を入れて微生物による発酵を促す。
またしても「発酵」である。
有機農業における頼もしい相棒が微生物であるように、藍染もまた微生物の力を借りるのだ。
藍の色素は発酵させてアルカリ性の水溶液に変換することで染料として使えるようになる。
ここで仕事をしてくれるのが、藍甕の中に宿る「藍還元菌」だ。
「藍建て」といわれる工程である。
発酵がうまくいくと、「藍の華」と呼ばれる泡が表面に現れる。
染めてもいいという合図だ。
発酵状態が良いと、きめ細やかな泡ができる。
発酵がうまくいかないと、染料液にならない。
「藍の花」がなくなってくると、藍がそろそろ疲れてきたサインである。
藍還元菌が元気に活動してくれるほど、色がたくさん溶け出す。疲れてくると色が溶けなくなり、あまり染まらなくなってしまう。
甕の中で藍は生きている。
染師は常に色やにおい、味などで藍の状態を判断し、子どもをあやすように機嫌を取りながら、この微生物が住みやすい環境に整えて増殖させ、色素を溶かしてもらうのだ。
それにしても、「どうやらこのブクブクが大事なようだ」「このブクブクの機嫌を損ねたらまずいぞ」と気が付くまでに、かつて人々は一体どれほどの失敗や試行錯誤を重ねたことか。
科学的に分析することも、原理を知る術もなかったのに、なぜこんな複雑で骨の折れる工程を編み出せたのだろうか。
少なくとも、自然界にあるものをコントロールしてやろうなどとは思っていなかったに違いない。