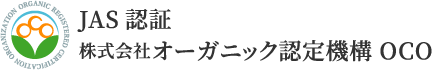使い捨てのライフスタイルを見直すことが環境保護につながるということは、もう誰もが知っている。
大量生産、大量消費、大量廃棄の時代から、循環型社会の時代へと変わらなければならない。
一人一人ができることからということで、例えばマイカップ、マイボトル、マイ箸を持ち歩こうという行動が生まれた。
身近な使い捨ての代表格が「割り箸」だ。
一時期、割り箸は資源の無駄遣いであり、環境破壊につながると批判された。
だが、全面的に悪者とも限らない、いや、むしろエコなのだと、見方が変わってきた。
わが国には古くから木の文化がある。
特にスギは、現代では花粉症を引き起こすというので悪者扱いのだが、縄文の昔から生活とともにあった木である。
真っすぐに空に向かって伸びる、日本で最も高くなる木だとか。
建築材や建具に使われ、船も造られたし、葉っぱはお線香の材料になった。新酒を知らせるスギ玉なんていうのもある。
割り箸もその一つだ。
箸は最初は神器として、そして聖徳太子の時代に随の使節をもてなすために初めて「箸食制度」が取り入れられ、その後一般にも箸食が広がった。
江戸時代になると鰻屋などの飲食店が大流行し、「引裂箸」(ひきさきばし)という2本の根元がくっ付いた竹製の箸が登場した。
割られていないものは未使用だと一目で分かるので、衛生面でも優れもの。
どうやら、ここから使い捨ての割り箸が始まったようである。
現在使われている割り箸は、奈良の吉野で樽に使っていたスギの端材の有効活用から生まれたといわれる。
「端材の有効活用」、ここがポイントである。
20年前、日本では年間250億膳もの割り箸が消費された。
そのほとんどが中国製の輸入品である。
中国では端材ではなく原木を全て割り箸に加工するため、使い捨ての木の割り箸は森林伐採、環境破壊につながると批判されるようになったのだ。
だが、繰り返すが、日本製の割り箸は端材や間伐材を有効活用して作られる。
定期的な間伐は、木が成長を妨げ合わないように森林を管理する上でとても大事なのだ。
そして、その間伐材はちゃんと資源として利用される。
問題は、国内生産されている割り箸が全体消費量のわずか2%ぐらいだということ。
輸入割り箸、そしてさらにプラスチック箸やマイ箸がいわれるようになり、1993年から2003年の10年間で国内の割り箸生産工場の数は半減したという。
ところが、ここにきて状況が変わってきた。
海外の割り箸ブームがけん引し、世界の割り箸市場が大きな成長を見せている。
割り箸はSDGsに貢献するものだと、消費者の見方が変わったのだ。
欧米ではプラスチック製のカトラリーの代わりに、木製や紙製が導入されている。
そんな中で、生分解性である木材を使った割り箸が木製カトラリーとして注目されるようになったのだ。
日本食や麺類などのアジア料理の普及で、いまや欧米人も箸を上手に使いこなす。
使い捨ての象徴のように扱われ批判された割り箸は、今はエコ製品だと評価されるようになり、これからさらに市場が拡大すると見られる。
日本の割り箸業界にとってはチャンス到来である。
ところが、海外の割り箸ブームに対して、日本国内ではかつて年間250億膳あった割り箸の消費が、今では約150億膳に減っているという。なんとも悩ましい現実である。
木と共生する中から生まれた割り箸。
国産材を使った割り箸の付加価値が見直されることは、日本の林業を支え、森林を守り、環境を守ることにつながる。
さらに、漂白剤、防カビ剤、防腐剤の残留など安全性の問題が心配される輸入割り箸よりも、国内産は安全性が高い。
持続可能な社会にするためには正しく知ることも必要だ。だが、何が正しいのか、見極めるのはとても難しい。
きちんと知り、きちんと考え、きちんと行動すること……ああ、反省の日々である。