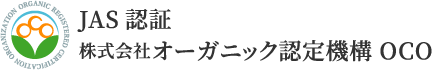「カカオショック」……チョコ好きにはまさにショック、大問題である。
世界の主要なカカオ生産国は、西アフリカのコートジボワールとガーナの2国。
2023年末から大雨・洪水、干ばつなどの異常気象に見舞われ、収穫量が減少した。
農地がダメージを受け、さらにカカオの木を枯らすウイルスがまん延し、感染対策として何億もの木が焼きはらわれたという。
圧倒的な供給不足。
そこに拍車を掛けているのが投機マネーなどの市場の動きだ。
カカオ豆の値段はニューヨークやロンドンの商品先物取引市場で決まる。
価格が一気に跳ね上がっても、農家の利益が増えるわけではない。
生産者には、カカオ豆の値段を決める力がない。
さまざまな仲介業者が入り、安く買い取られ、生産者に利益が還元されにくい。
チョコレートを消費するのは豊かな国で、生産するのは貧しい国、そんな構図がずっと続いてきたのである。
日本でもチョコレートの値上げが相次いだ。
カカオ豆が調達できなければ商品価格を上げざるを得ないわけだが、そもそもの供給量が減ってしまっているとなれば、値上げだけではたちゆかない。
カカオたっぷりの純粋なチョコは高嶺の花になってしまうのか……。
カカオは農作物である。
とてもデリケートで、木が育つ環境は限られているし、植えてから収穫までにおよそ5年もかかるのだ。
当然、自然の影響を受ける。
栽培から収穫、そして発酵させて乾燥させてと、重労働である。
だが、相場は生産者の努力とは関係のないところで左右されている。
現地のカカオ農家は自分の子どもには同じ仕事を継がせたくないという。
だが、村にはカカオ栽培しか仕事がない。
外に出てほしい、そのためには学問が必要だ。
親たちは子どもに教育を授けるために懸命に働いているのだ。
そんな中、カカオ豆など、たくさんの問題をはらんでいるカカオ生産を取り巻く悪しき構造を変えようという取り組みも起きている。
仲介業者を介さずに生産者から直接カカオ豆から仕入れる。
あるいは、産地におけるカカオ豆栽培の支援からチョコの製造・販売まで一貫して自社で行う企業も現れている。
労働に見合った収益、安定した収入は当然受け取ってよい権利である。
環境に配慮した栽培で付加価値を付け、それが収入向上につながれば、やりがいが生まれる。品質への誇りがさらなる付加価値の追求へと突き動かす。
生産者も消費者も幸せになれる循環になる。
疲れた時に一粒のチョコがエネルギーとなったり、甘いチョコを食べて幸せな気持ちになったり、そんな経験がきっとあるだろう。
チョコレートの持つ不思議な力が人々の気持ちを変えていく『ショコラ』という映画もあった。
だが、カカオ産地の子どもたちは、労働に駆り出されるだけで、育てたカカオ豆から生まれるチョコレートのあの甘い幸せを知らないというのだから、こんな悲しいことがあるだろうか。
ちまたではバレンタイン商戦たけなわである。
日本ではチョコレートの年間の消費量の2割がこの時期に消費されるとか。
原料のカカオを作った彼らは、一体これでどれだけの収入を得たのだろうか。
あれこれ考えると、義理とか本命とか、友チョコ、ファミチョコなんて言っている場合ではないと思い直す。
そして、少しでも持続可能なカカオの生産につながるものをと、手に取るチョコを意識して選び直す。小さな行動だが、意思を持って。